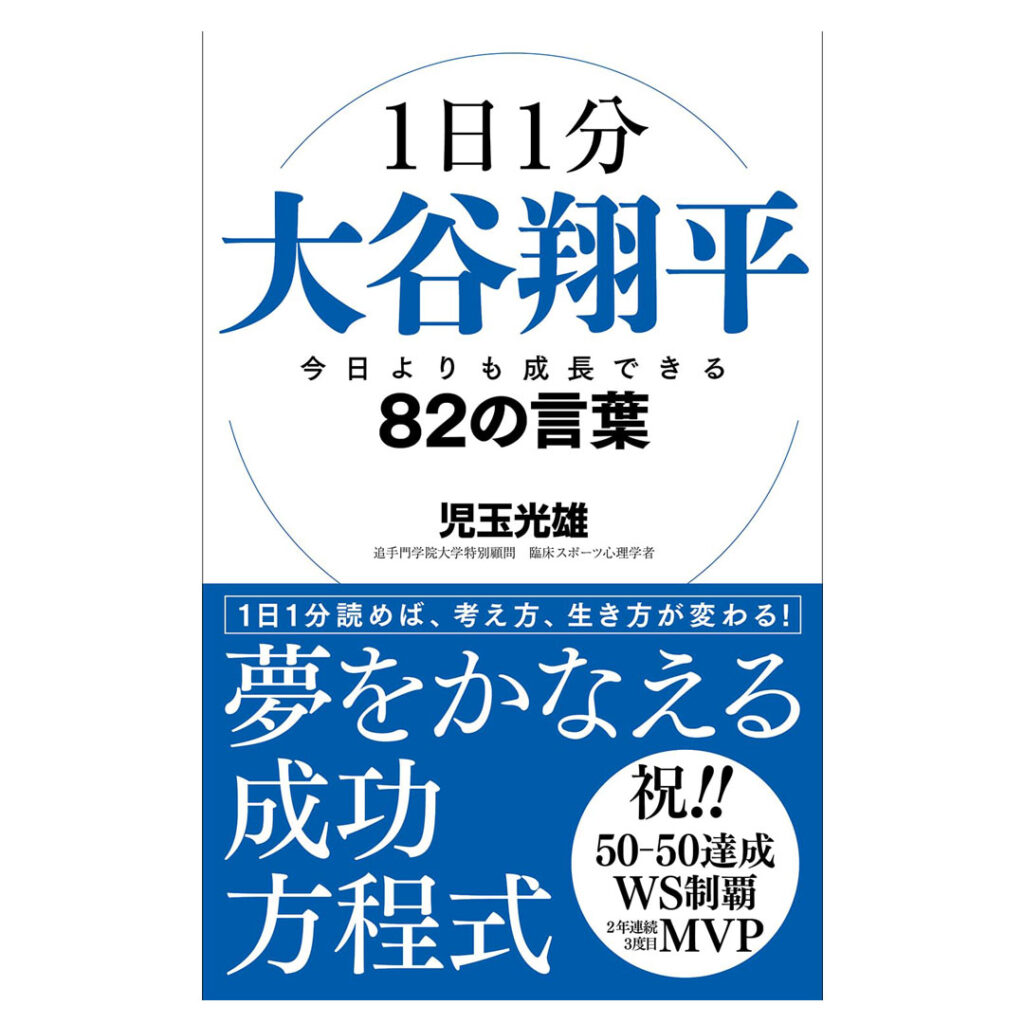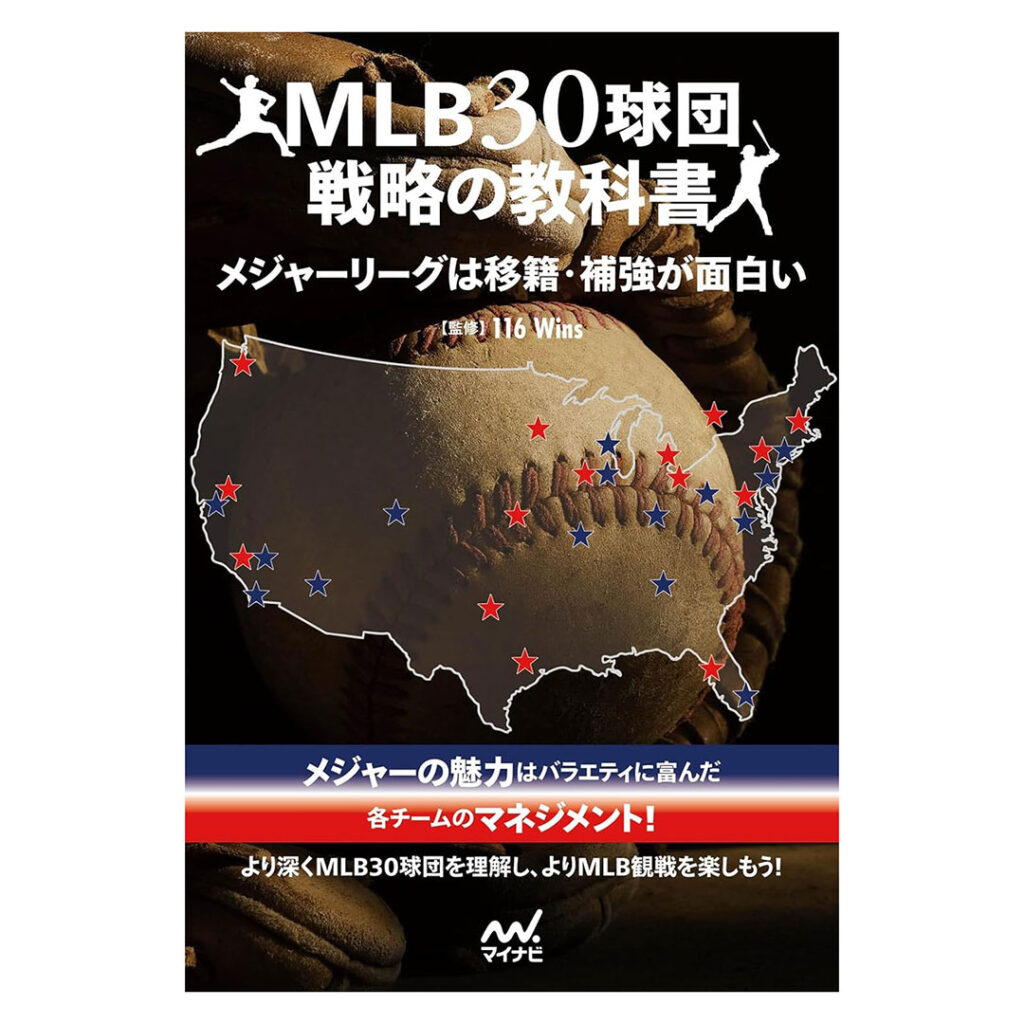ジム・リーランドが昨年8月にパイレーツの殿堂入りを果たした数時間後、記者たちに囲まれて話していたとき、彼は現在のバッカニアーズ(パイレーツの愛称)と1990年代初頭の自身が率いたチームを比較してほしいと求められました。それは不可能な課題です。なぜなら、その地区優勝チームには、のちに通算本塁打記録保持者となる選手(バリー・ボンズ)がいたからです。しかし、リーランドはその求めに応じました。
「彼らにはバリー・ボンズはいないだろうね」とリーランドは言いました。「でも、ダグ・ドレイベックなら間違いなくいるよ。」
過去のアスリートと比較するのは、ピッツバーグのようなスポーツ熱の高い街の特徴の一つです。チームへの情熱が深く根付いているこの街では、共有された経験や記憶が一つの“共通言語”となり、ある状況や選手を過去の誰かになぞらえて説明することができます。例えば、「中軸を担えるベテランの外野手がいればチームはもう一段階上に行ける」と長々と説明する代わりに、「彼らには“マーリン・バードのトレード”が必要だ」と言えば、2013年のあの瞬間を知るファンなら、I.C.ライト(地元のビール)を片手にすぐ理解してくれるでしょう。ブルペンに“信頼できる左の8イニング投げれる投手”が必要だと言うより、「トニー・ワトソンが必要だ」と言えば、全てが通じるのです。

何十年もの間、ピッツバーグの人々が「エース級の投手が必要だ」と語るとき、その代名詞として挙げられてきたのがダグ・ドレイベックです。大一番で頼りになり、チームを勝利に導いてくれる22勝投手――それがドレイベックのイメージです。
「エースになるっていうのは、何年もかけて築くもので、長期間にわたってその座にいる必要がある」とドレイベックは電話インタビューで語りました。「……自分としては、良い投球をして、安定していることを目指していたんだ。それが結果的に『エース』と呼ばれるようになったなら、それはそれで良いし、そうでなくても、チームに貢献できていれば、それが一番大事だったと思う。」
その安定した活躍により、ドレイベックは個人としても高く評価されました。その頂点が、1990年のサイ・ヤング賞の受賞です。彼自身は、その賞を獲る有力候補だと感じていたわけではありませんでしたが、その年パイレーツが地区優勝へと突き進む中、彼はサイ・ヤング賞の投票でほぼ全ての1位票を獲得し、頂点に立ちました。
1956年にサイ・ヤング賞が創設されて以来、パイレーツからこの栄誉を手にした投手はわずか2人――ダグ・ドレイベックとヴァーン・ロー(1960年)しかいません。非常に限られた特別なグループですが、近い将来、このリストに新たな名前が加わる可能性があります。
「もし誰かがそこに自分の名前を加えることができたら、それも素晴らしいことだね」とドレイベックは語ります。
その「誰か」となる可能性を秘めているのが、ポール・スキーンズです。少なくともここ一世代の中で初めて、パイレーツはローテーションの先頭にサイ・ヤング賞の最有力候補を擁してシーズンを迎えることになります。ファンたちが熱狂的に待ち望む“続編”――スキーンズの圧巻の新人王シーズンに続く活躍は、彼の登板が見逃せない特別な瞬間となっています。
卓越と勝利を追求する姿勢――空軍士官学校で培われたその勤勉さによって、ポール・スキーンズは誰もが知る存在となりました。しかし、彼は決して「ロックスタータイプ」ではありません。その名声と圧倒的な投球内容によって公の注目を浴びるようになったものの、パイレーツにドラフト指名された20か月前と比べて、基本的には変わらない人物です。唯一の違いは、自身の「仕事=ショー」と化した環境に、少しだけ慣れてきたことかもしれません。
それは、時にメディアに冗談を飛ばす姿や、LECOMパークのクラブハウスで先発投手陣がミニバスケットボールを楽しむ中、アシスト役を務める姿に表れます。
スキーンズのそんな人柄を象徴するのが、2024年ナショナル・リーグ新人王に選ばれた夜に生まれた、あるミーム(インターネットで話題となった画像)です。歓喜の瞬間、スキーンズは数秒間、驚くほど無表情のまま――そしてついに、ふっと微笑みを浮かべたのでした。
「スキップ(監督)に呼ばれて、開幕戦の先発を伝えられたときも、反応はほとんど同じでした。これが自分なんです」とスキーンズは語りました。「開幕戦に先発するって知らなかったし、新人王を獲るとも知らなかった。これが自分なんです。両親やガールフレンドにも聞いてみてください。昔からずっとこうなんです。」
スキーンズは木曜日、ローンデポ・パークでマーリンズを相手にパイレーツの先発として今季最初のマウンドに立ちます。対戦相手の先発は、2022年のサイ・ヤング賞投手、サンディ・アルカンタラ。近い将来、我々はこの試合を「最近のサイ・ヤング受賞者と未来の受賞者による対決だった」と振り返るかもしれません。
そしていつの日か、ピッツバーグのファンたちが「登板するたびに観客を魅了する投手が必要だ」と感じたとき、こう簡潔に語ることになるかもしれません――「ポール・スキーンズのような投手が、また必要だ」と。
スキーンズのように急速な成長を遂げた投手はほとんどいません。2022年には空軍士官学校であまり知られていない二刀流選手だった彼は、2023年に大学野球の全米王者となり、ドラフト全体1位指名を受け、2024年にはナ・リーグ新人王に輝きました。個人の栄誉という点では、次の論理的なステップはサイ・ヤング賞であり、昨年わずか23先発で同賞の投票3位に入ったことを考えると、十分に可能性のある話です。
新人王を受賞した翌年にサイ・ヤング賞を獲得した投手は、MLB史上ただ1人――ドワイト・グッデンだけです。彼は1984年に新人王、1985年にサイ・ヤング賞をメッツで受賞しました。
グッデンは、近年で数少ない「極めて大きな期待を背負いながら投げ、しかもその期待に応えた」投手の1人です。それは若き選手にとって精神的な重圧になることもあります。グッデンは、フェルナンド・バレンズエラとの対戦で好投しながらも、奪三振数がわずか4にとどまった試合を振り返り、試合後のインタビューでそのことを問われた際には丁寧に答えつつも、「なぜ4個しか奪えなかったのか」という問いを長く引きずってしまったと語っています。
「若いうちに大きな成功を収めると、自分自身に対しても含めて、期待がどんどん高まっていくものだ」とグッデンは語ります。「時には、自分自身が非常に高い基準を設定してしまい、その後のすべての結果がその基準と比較されてしまう。彼には、常に自分が何を目指しているのか、何を達成したいのかを忘れず、自分自身を見失わないでいてほしい。つまり、周囲の雑音に惑わされず、自分のやるべきことに集中すべきということだ。」
スキーンズは、自身にかかる信じられないほどの期待とプレッシャーを理解しています。
しかし、誰よりもスキーンズ自身が、自分に最も高い期待をかけているのです。
「むしろ、自分は他人の期待に合わせて投げる方が“基準を下げている”って考えている」とスキーンズは語ります。「自分が自分に課している期待は、周囲の誰の期待とも違うし、周りの期待は自分にとって重要ではない。グッデンの言うことは間違っていないよ。だって、周囲にはサインを求める人が大勢いるし、それは自分が良い投球をしなければ実現しないものだから。」
「そういうのは素晴らしいけど、結局のところ、自分の中にあるものだけが、自分が夜にどれだけ安らかに眠れるかを決めるんだ。」
スキーンズは、外部の雑音を無視するよう努力しています。自分に関する記事を読まないようにし、SNSからも距離を置いています。それでも、時には避けられないこともあります。
スプリングトレーニング最後の登板前、ウォームアップ中のスキーンズに、ファンがこう声をかけました。「今日はノーヒッターを頼むよ!」――普通なら荒唐無稽なリクエストですが、スキーンズがマウンドに立つと、なぜかそれが現実味を帯びてくるのです。
昨年、スキーンズは6イニング以上を無安打に抑え、11奪三振以上を記録して降板した試合が2度ありました。この条件を同じシーズン中に複数回達成したのは、1973年のノーラン・ライアンだけです。
皮肉なのは、その2試合の直前、スキーンズは「最悪の体調だった」と感じていたことです。ブリュワーズ戦での快投前は「気分が最悪」で、カブス戦ではMLBでのわずか2度目の先発だったこともあり、ノーヒッターなどまったく意識していなかったと言います。
「その2試合って、実は何の期待もせずにマウンドに上がったんだよね」とスキーンズは語ります。「期待を背負わず、ただ無心で投げて、実行する。それが功を奏したんだと思う。」
「だって、最悪何が起きるの?点を取られる?それがどうしたって言うんだ?」と、スキーンズは笑いながら語りました。
その「開き直ったような投球スタイル」は、彼の100マイル超えの速球や世界屈指の「スプランカー(スプリット+シンカー)」と並ぶ才能と言えるかもしれません。
昨年、スキーンズがドジャースと初対戦した際、最初の打席では大谷翔平から3球連続の速球で三振を奪いましたが、2打席目には本塁打を浴びました。その時、スキーンズは大谷がベースを回る姿を見ながら笑みを浮かべていました。三振も本塁打も、「ビッグ対ビッグの対決ではよくあることさ」と、勝負を潔く受け止めたのです。
2025年のシーズンを迎える今、スキーンズほど「ビッグな存在」はほとんどいません。
「“ワオ”っていう瞬間は自分で作ろうとして作れるものじゃない。自然に起きるものだ」とスキーンズは言います。「正直、自分自身を見つめ直すと、“ワオ”と思える瞬間っていうのは、たいてい予想してないときに起きてる。そういう瞬間は、毎回正しく、しっかりと投球を重ねていった結果として訪れる。誰かがブルペンで『やれ!』って言ったから起きるわけじゃないんだよ。」
PNCパークの通路を歩くと、球団の歴代受賞者たちの壁画が並び、ホームクラブハウスへと続きます。そこには100年以上前の選手たち──首位打者ジンジャー・ボーモントやホーナス・ワグナー、ナ・リーグMVPポール・ワーナー──の姿もあれば、現代の選手たち──ゴールドグラブ賞を獲得したケブライアン・ヘイズやジャレッド・トリオロ、そしてMVPのアンドリュー・マカッチェン──の姿もあります。
Paul Skenes officially received his 2024 National League Rookie of the Year Award at the 2025 BBWAA Awards Dinner in New York. pic.twitter.com/9XkZ80cdP4
— Pittsburgh Pirates (@Pirates) January 26, 2025
投手部門においては、ゴールドグラブ賞やシルバースラッガー賞の受賞者がちらほらいる中で、ロウとドラベックの名は特別な存在として際立っています。これらの壁画は過去を称える目的で作られていますが、その裏には「この球団には何十年もリーグ最高の投手がいなかった」という暗黙のメッセージが感じられるのです。
そして今、スキーンズは球団の顔であり、全米の野球ファンが5試合ごとにアレゲニー川のほとりに注目する主な理由のひとつとなっています。その存在感はあまりにも明白で、すでにパロディの題材にされるほどです。今月初め、MLBネットワークがフロリダ州ブレーデントンのパイレーツ春季キャンプを取材した際のオープニング映像では、スキーンズがアンドリュー・マカッチェンにテーピングをしており、マカッチェンが若きスターターに向かってこう語ります──「うまくやれば、そのうち君の名も知られるようになるさ。ロベルト・クレメンテ、ウィリー・スタージェル、そしてもちろんアンドリュー・マカッチェンのようにね。」
スキーンズがいつの日か「球団史上最高の選手」として語られる可能性もあるでしょう。球団の歴史、そして近年の成功の欠如──その重みは確かに感じられます。チームの顔としての期待を感じているかと問われた際、スキーンズは「はい」や「いいえ」とは答えませんでした。代わりに、金の腕と無限の可能性を持つ22歳の若者は、自身を突き動かす原動力を垣間見せました。
「この街に対して、俺たちは何かを返す義務があると思ってる。たくさんのものを受け取ったんだから。それを返す方法は、街のために勝利を重ねること。それが俺たちの仕事だ。これは俺たち一人ひとりのためじゃない。もっと大きなものなんだ。マカッチェンが何度も戻ってくる理由も、ピッツバーグという街に特別な何かがあるからなんだ。去年の夏にその一端を見たし、ワイルドカードゲームの映像にも映っていた。でも俺はあの映像をもう見たくない。あれはワイルドカードシリーズだったんだ。俺たちはもっと高い基準を目指さないといけない。あのチームの功績を否定するつもりはない。でも、あの時代が最近のパイレーツ野球の黄金期として扱われてること自体が変わらなきゃいけない。街に対して、俺たちはそれだけの責任がある。」
だからこそ、ドラベックやロウ、そしていつかスキーンズの名が並ぶとしても、それは「ピッツバーグ投手界の王者」を目指す旅ではありません。彼らと同じように、この街に勝利をもたらすという使命を追い求めているのです。
「俺たちには受け継がれた伝統がある。その火を絶やしちゃいけない。前の世代がジャージー(=球団)をより良い形で後に残してくれた。俺もそうしたいし、俺たち全員がそれを目指してるんだ。」
アレックス・スタンプ:MLB.com パイレーツ担当
引用元:mlb.com